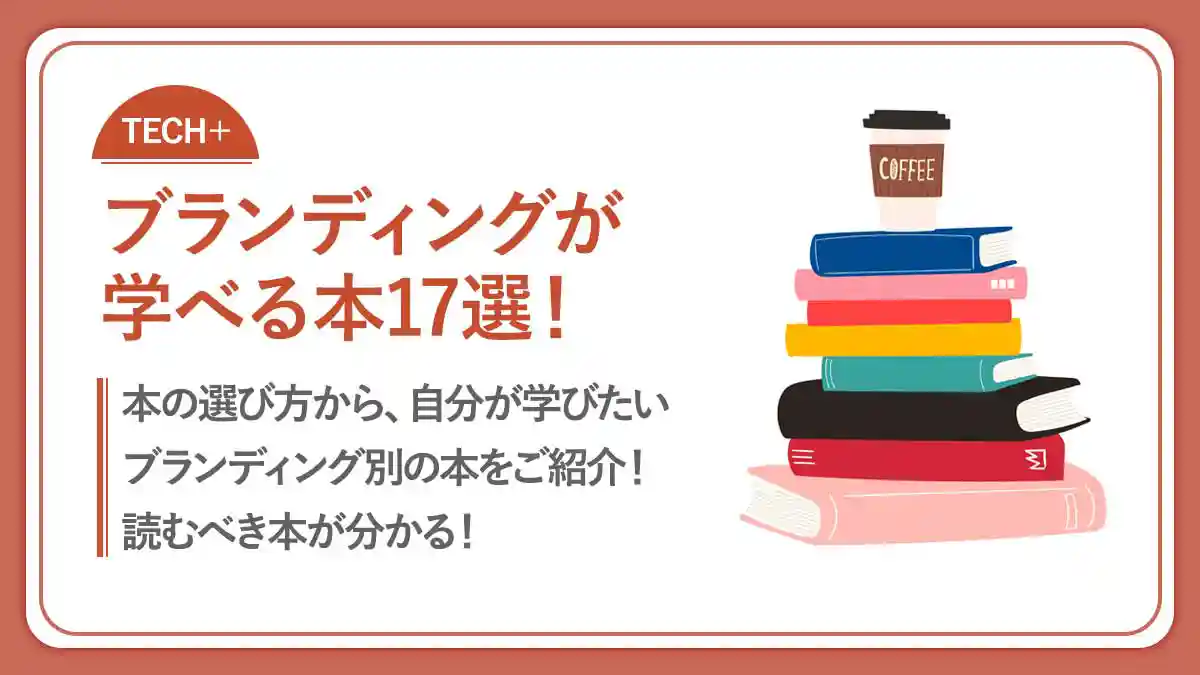採用ブランディングとは?効果や手順、取り組み企業の事例まで紹介
認知拡大・ブランディング
【TECH+マーケティング責任者】武本 大平 [2023.07.28]
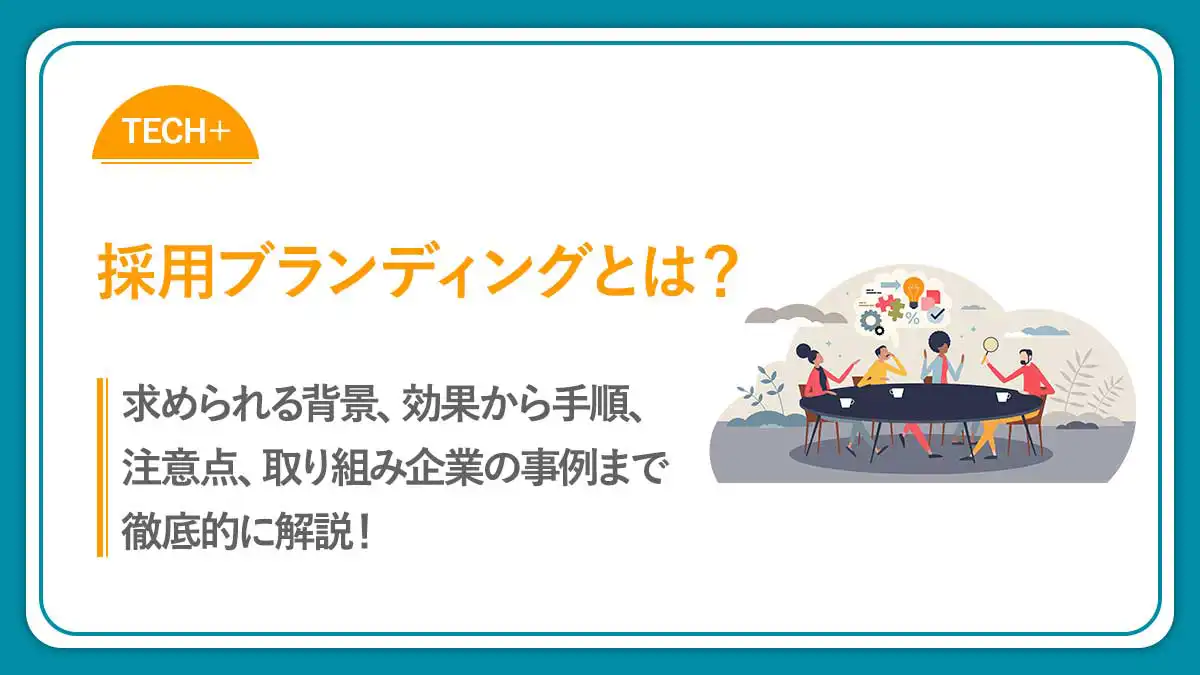
目次
- 【1】採用ブランディングの概要
- 1.ブランディングとは
- 2.採用ブランディングとは
- 【2】採用ブランディングが注目される背景
- 【3】採用ブランディングの効果
- 1.企業認知度の向上
- 2.応募者数の増加
- 3.人材獲得競争の回避
- 4.採用コストの削減
- 5.採用ミスマッチの防止
- 6.従業員エンゲージメントが上がる
- 【4】採用ブランディングの進め方
- 1.自社で働くメリットを発見する
- 2.求める人物像を描く
- 3.情報発信の手段を検討する
- 4.コンテンツを用意する
- 5.従業員に周知する
- 6.振り返りを行う
- 【5】採用ブランディングを進める上での注意点
- 1.ブランディング効果が出るまで時間がかかる
- 2.中長期的な目標を設定する
- 3.誇張してしまうと採用ミスマッチが起きる
- 4.全社的に取り組まなければ成果が出ない
- 5.リソースを用意する必要がある
- 【6】採用ブランディングに取り組む企業事例
- 1.日本マクドナルド株式会社
- 2.株式会社LINE
- 3.サイバーエージェント株式会社
- 4.SONYグループ株式会社
- 【7】まとめ
【1】採用ブランディングの概要
まずは、採用ブランディングについて理解できるように概要を説明します。
1.ブランディングとは
ブランディングとはターゲットに対して企業の印象を良くするための取り組みです。ブランディングに成功すれば、ターゲットが「このような商品が欲しい」「このような場所に行きたい」と思ったときに自社の商品・サービスを最初に思い浮かべてもらうことができます。
例えば、求人サービスといえばマイナビのように思い浮かべてもらえるようになれば、長期的な利益が確保できるようになります。
下記の記事でBtoB企業のブランディングについて詳しく解説しています。
・[成功事例付き]BtoBブランディングとは?種類・進め方・学習方法まで解説
2.採用ブランディングとは
採用ブランディングとは求職者に対して企業の印象を良くするための取り組みです。求職者に「企業理念やビジョンに共感したから働いてみたい」「仕事と家庭の両立がしやすい職場だから、求めている職場にピッタリだ」と思ってもらうための施策です。
さまざまな求人がある中で自社の求人に興味を持ってもらうために戦略的に情報を配信していくことをいいます。
【2】採用ブランディングが注目される背景
採用ブランディングが注目される背景には、労働者不足の問題があります。株式会社帝国データバンク『人手不足に対する企業の動向調査(2022年10月)』では、労働者不足の数値の上昇は歯止めがかからないと述べられています。同調査によると労働者不足で悩んでいる企業は、正社員で51.1%、非正規社員で31.0%にも及ぶのです。
就職・転職市場が売り手市場になってきているため、優秀な人材が獲得しにくくなってきています。企業は求職者に選んでもらうために労働条件だけでなく、事業内容や一緒に働く人など、その他の魅力を積極的に発信していかなければいけなくなってきたのです。
このような背景により、採用ブランディングが注目されるようになりました。今後、自社のファンを増やしていく採用ブランディングは、ますます重要な施策になっていくとも言われています。
【3】採用ブランディングの効果
採用ブランディングに取り組むと得られる効果は6つあります。
1.企業認知度の向上
自社の情報を積極的に発信していけば、多くの人に情報が届けられます。
求人広告や人材紹介のサービスを利用すると、転職顕在層(転職活動をしている人)にアプローチできますが転職潜在層(良い会社があれば転職したい人)にアプローチできません。
しかし、採用ブランディングに取り組んで情報を発信していけば、転職潜在層にもアプローチできます。「あの会社は、理想の働き方ができる会社だ」と浸透していけば、人材獲得で悩むこともなくなるでしょう。このように、企業認知度の向上が採用ブランディングのメリットです。
2.応募者数の増加
自社の求人に興味を持ってもらうために戦略的に情報配信していけば、より多くの人に見てもらえるようになります。また、自社で働く魅力(事業内容や職場環境、福利厚生など)をアピールすれば、求職者は「この会社が気になる」と興味・関心を持ってもらえるようになるでしょう。
就職・転職市場は売り手市場が続いており、求人を出しても人が集まりにくくなっていますが採用ブランディングに取り組めば、より多くの応募が獲得できます。
3.人材獲得競争の回避
競合他社と差別化できる自社の魅力を伝えていくことができれば、人材獲得競争に巻き込まれずに済むようになります。なぜなら求職者にとって自社の存在が「唯一無二の存在」となるためです。
労働条件など他社と同じものを書くだけでは、どうしても人材獲得競争に巻き込まれてしまいます。人材獲得競争に巻き込まれてしまうと、採用フローが増えて人事担当者も苦労してしまいます。
その一方で、唯一無二の存在になれば他社と比較されることはありません。このような労力を減らすためにも採用ブランディングに取り組んで人材獲得競争を回避していきましょう。
4.採用コストの削減
採用ブランディングに取り組むときは、リソースがかかります。短期的に見ると、採用ブランディングを目的としてメディアやSNS運営費用や広告費用、外部コンサルタント費用は高く感じてしまうでしょう。
しかし、中長期で見ると採用コストが削減できます。例えば、SNSのフォロワー数が増えていけば、求人情報を投稿するだけで該当者が立候補してくれるようになります。このように求人広告や人材紹介のサービスを使う必要がなくなれば、採用コストが抑えられるのです。
5.採用ミスマッチの防止
採用ブランディングを目的にオウンドメディアやSNSを運営していくと、「事業内容」「企業理念」「ビジョン」「一緒に働く人」「働く環境」など、あらゆる情報を発信していくことになります。
さまざまな情報を発信していくことになるため求職者は応募する前に「どのような会社なのか」がイメージしやすくなります。企業について理解を深めた上で応募してくるようになるため、入社後のギャップが出なくなるのです。
企業情報が少ないと「この上司とは気が合いそうもない」「想像していたより、個人プレーの仕事だった」と悩みを抱え出して、早期離職してしまうかもしれません。このような採用ミスマッチが防止できます。
6.従業員エンゲージメントが上がる
採用ブランディングに取り組んでいくと既存社員が「私たちの会社は他社と比較して、こんな魅力があるんだ」と気づきが得られて、従業員エンゲージメントを上げていけます。
従業員エンゲージメントが上がれば、1人1人が意欲的に働いてくれるようになり「生産性の向上」「顧客満足度アップ」「事故発生率の低下」などの効果が得られるのです。
また、採用ブランディングで世間に企業が認知されれば「この会社に勤められて良かった」と思ってもらえるようになります。
【4】採用ブランディングの進め方
さまざまな効果が見込める採用ブランディングの進め方は以下の通りです。
[採用ブランディングの進め方]
- 自社で働くメリットを発見する
- 求める人物像を描く
- 情報発信の手段を検討する
- コンテンツを用意する
- 従業員に周知する
- 振り返りを行う
ここでは、各手順について詳しく解説します。
1.自社で働くメリットを発見する
まずは、競合他社と比較して自社で働くメリットとは何かを考えていきます。自社で働くメリットを考えていくためにSWOT分析を活用するようにしましょう。SWOT分析は「強み」「弱み」「機会」「脅威」という4つの観点から現状を分析していくフレームワークです。
SWOT分析
|
|
Sterngth(強み) |
Weakness(弱み) |
|
Opportunity(機会) |
自社の強みを機会に活かして大きく成長できる |
弱みを補強して機会を活かせるように対策する |
|
Threat(脅威) |
強みを活かし脅威を避けたり機会として活かす |
弱みを理解し、脅威を避けたり影響を最小限にする |
自社で働くメリットは具体的に出しておくようにしましょう。そうすることで、採用ブランディングのための情報発信が行いやすくなります。
2.求める人物像を描く
次に自社が求める人物像(ペルソナ)を描いていきます。どのような人物像が欲しいかを考える場合は、以下の項目を外さないようにしましょう。
[ペルソナの項目]
- 年齢
- 男女
- 学歴
- 年収
- 経験
- 資格
- 価値観
- 人柄
ペルソナは、人事担当者が独断で設計してはいけません。経営者や現場リーダーにヒアリングして、どのような人物を求めているかをヒアリングした上で設計していきましょう。
3.情報発信の手段を検討する
求めている人物像を描けたら、ペルソナがどのような求人情報をどのように収集するかを考えていき、自社の情報が届く情報発信の手段を検討していきます。求人に関する情報の発信チャンネルやコンテンツ形態には、以下のようなものがあります。
[発信チャンネルの種類]
- 自社サイト(求人情報ページ)
- 採用向けオウンドメディア
- 口コミサイト
- SNS(Twitter・Facebook・Instagram)
- セミナー
- 会社説明会
[コンテンツの形態]
- テキスト
- 写真
- 動画
- イラスト
- パンフレット
- ノベルティグッズ
4.コンテンツを用意する
情報発信の手段を検討したら、コンテンツを制作していきます。コンテンツを制作する場合は、自社が求めている人物像が興味を引くようなコンテンツを用意することが大切です。
魅力的なコンテンツ作る場合は、写真や動画、イラストを作成しなければいけないこともあります。社内で魅力的なコンテンツが制作できないと感じたら採用ブランディング支援会社に相談するのも1つの選択肢です。
自社の強みである内容から発信すべきですが、どのような情報を発信していけばよいか悩んだら、以下を参考にしてみてください。
[コンテンツの例]
- 社員インタビュー
- 経営者インタビュー
- キャリア紹介
- オフィスの様子
- 企業文化や歴史の紹介
- 1日の過ごし方
- 1年間の行事
- 社員ブログ
- 独自の採用プロジェクト
5.従業員に周知する
採用ブランディングに取り組み始めたら、その旨を従業員に周知しましょう。なぜなら従業員が求職者、取引先、顧客と関わるときにブランドを理解して体現することでブランドに浸透促進ができるためです。
例えば、求人広告に自社の魅力を掲載したにも関わらず、会社説明会で先輩社員が、そのような魅力を説明できなければ、求職者は不信感を抱いてしまうかもしれません。このような問題を防止するため、従業員に自社のブランドについて理解してもらうようにしましょう。
[従業員に周知する方法]
- ディスカッション
- グループワーク
- 座学
- eラーニング
6.振り返りを行う
採用ブランディングに取り組んだら、必ず振り返りを行うようにしましょう。採用ブランディングに取り組んでから、求人に対する応募数や採用数をチェックして、効果を測定していきましょう。
結果が出ていない場合は、どこに問題があるか意見を出しあったり、成功事例と比較してどこに問題があるかを確認したりしましょう。また、上手くいかないと悩んだときは、採用ブランディング支援会社に相談するのも1つの選択肢です。
【5】採用ブランディングを進める上での注意点
採用ブランディングの進め方をご紹介しましたが、取り組む上での注意点を覚えておきましょう。
1.ブランディング効果が出るまで時間がかかる
採用ブランディングに取り組めば、すぐに効果が見込めるものではありません。なぜなら、ブランディングは、ターゲットに好印象を少しずつ与えていくための施策のためです。実際に取り組んでみると、想像よりも地道な作業に感じてしまうこともあるでしょう。
企業や施策によって、効果が見込める期間は異なりますが、採用ブランディングを途切れることなく継続すれば1年で何らかの効果が見込めるはずです。そのため、採用ブランディングで効果を見込むためには時間がかかると理解しておき、まずは1年間取り組んでみましょう。
2.中長期的な目標を設定する
採用ブランディングの効果が出るまで時間がかかると説明しました。何か物事に取り組むときは、短期的な目標を立ててしまいがちです。
例えば「オウンドメディアを立ち上げて3ヵ月後に、メディア経由で応募を獲得する」というような短期目標を立ててしまうと、効果が出ないと落ち込んでしまいます。その結果、採用ブランディングの取り組みが続かなくなってしまうのです。
このような問題を防止するために、5年、10年を見据えて「知名度を上げて、仕事探しのときに自社を思い出してもらう」「情報を提供して採用ミスマッチを防止する」などの中長期の目標を立てるようにしましょう。
3.誇張してしまうと採用ミスマッチが起きる
採用ブランディングは、求職者に「このような会社で働いてみたい」と思ってもらうために情報発信していく取り組みをいいますが、誇張してしまうと採用ミスマッチが起きてしまいます。
例えば、社員の1日の過ごし方を情報で提供した際に、9時から18時のタイムスケージュールにしたにも関わらず実際は残業が蔓延していたら、入社前後でギャップを感じてしまいます。このようなギャップを感じてしまうと、会社に対して不信感が芽生えて、働く意欲も減退してしまうかもしれません。
早期離職やモチベーションの低下など、さまざまな問題が出てくるため、誇張した情報を発信しないようにしましょう。
4.全社的に取り組まなければ成果が出ない
採用ブランディングは、人事担当者が情報配信していけばよいものではありません。会社全体で採用ブランディングに取り組む必要があります。なぜなら「求職者にどのような企業イメージを持ってもらいたいか」を共有して全員でブランドを体現していく必要があるためです。
例えば、人事担当者が採用サイトに「ビジョンがあり、働きがいのある職場だ」と述べても、会社説明会で先輩がビジョンを話せないと求職者は困惑してしまうでしょう。その結果、採用ブランディングが失敗に終わってしまうのです。このような失敗を防止するためにも、全社的に取り組んでいくようにしましょう。
5.リソースを用意する必要がある
採用ブランディングに取り組むためには、「どのようなターゲットに」「どのような手法で」「どのような情報を」提供していくかを考えて、コンテンツを制作していきます。
コンテンツを制作するときには、クリエイティブにこだわらなければいけなかったり、必要に応じて社内の人にインタビューしたりしなければいけません。そのため、採用ブランディングに取り組むためにはリソースが必要になります。
リソースを確保せずに、通常業務に追加業務としてやらせると、従業員から反感を買ってしまうかもしれません。そのため、採用ブランディングに取り組むためのリソースを確保しておくようにしましょう。もし、社内でリソースを確保できない場合は、採用ブランディング支援会社に相談するのも1つの方法です。
【6】採用ブランディングに取り組む企業事例
採用ブランディングの進め方は理解できたと思いますが、実際にどのような配信手段で、どのようなクリエイティブを制作していけば良いのでしょうか?このような悩みを抱えたら、採用ブランディングに取り組んでいる企業事例を参考にしましょう。
1.日本マクドナルド株式会社

出典元:『日本マクドナルド株式会社』
日本マクドナルド株式会社は店舗で働くクルーを主役と考えており、経営陣や本社で働く人は「クルーを支える立場」として位置付けられています。
マクドナルドの創業者レイ・A・クロックは「マクドナルドはハンバーガービジネスではない、ハンバーガーを打っている“ピープルビジネス”である」という言葉を残しました。
そのような同社はクルー採用のために採用ブランディングに取り組んでおり新たな採用手法の開発やオウンドメディアからの応募促進を行っています。
自社の魅力として、クルーの働きやすさを重視しています。また、クルーで活躍したい方向けにリーダーシップやマネジメントが学べる「ハンバーガー大学」を運営するなど、活き活きと働ける職場づくりに努めているのです。
同社の採用サイトには「マクドナルドで働くメリット」が豊富に掲載されているため、採用ブランディングの見本におすすめです。
2.株式会社LINE

出典元:『株式会社LINE』
株式会社LINEは、全社的に採用ブランディングに取り組んでいる会社です。
1年間で約700名が入社をしてきていますが、その割合は人材紹介60%、リファラルリクルーティング(20%)、採用サイト10%、その他10%となっています。
同社はその中でもリファラルリクルーティング(従業員の紹介による人材採用)の比率を増やしたいと述べています。
リファラルリクルーティングの比率を上げるためには、社員による口コミ(自発的な発信)が欠かせません。しかし、同社は従業員に広報活動の協力を強制しているわけではないのです。
情報を発信したいという従業員の意見を尊重して、ブログ運営を任せたり、SNS運営を任せたりしています。このような従業員の意見を尊重することで、良い口コミが拡がる環境、仕組みを作っています。
3.サイバーエージェント株式会社

出典元:『サイバーエージェント株式会社』
サイバーエージェント株式会社は、優秀なエンジニアを採用するために他社のイベントで開発技術を教える登壇者として出て、自社の仕事に興味を持ってもらうという取り組みを行っています。
イベントの登壇では、エンジニアの開発技術を指導するだけでなく、自分のシステム開発に対する思想、未来像を述べるなど、イベント参加者が共感したり憧れたりするようなスピーチ内容になっています。
イベントの最後に、登壇者の部門でエンジニアを募集していることを告知して、多くの応募を獲得しています。このように、従業員が採用ブランディングを体現するという手法もあります。また、他企業のイベントやメディアとタイアップするのも1つの方法です。
4.SONYグループ株式会社

出典元:『SONYグループ株式会社』
SONYグループ株式会社は就職先として人気があり、競争倍率が高い企業として知られていますが、他社と差別化ができていることが大きな勝因です。
同社は「自分のキャリアは自分で築く」というカルチャーに根差ざした全98コースからファーストキャリアを選択できる新卒採用が用意されています。細かくコースが別れている理由は、働く一人ひとりが納得感を得られるようにするためです。
また、個々が築いたキャリアをどのような事業、経営に活かしていくかを考慮しています。
それだけでなく、働く上で進みたい道が変わってくることもあるかもしれません。そのような悩みを相談できる「1対1の個別面接」が用意されています。このように「自分のキャリアは自分で築く」というカルチャーがブランドとなって、多くの人材の採用に成功しています。
【7】まとめ
採用ブランディングとは、求職者に対して企業の印象を良くするための取り組みです。求職者に「企業理念や価値観に共感したから働いてみたい」「仕事と家庭の両立がしやすい職場だから、求めている職場にピッタリだ」と思ってもらうための施策です。
採用ブランディングに取り組めば求人の応募数が増えたり、人材獲得競争に巻き込まれずに済んだりします。また、社内で働く従業員のエンゲージメントを上げることも可能です。この記事では、採用ブランディングの進め方をご紹介したため、参考にしながら取り組んでみてください。
マイナビでは、IT会社や製造会社向けの採用ブランディング支援サービスを提供しています。マイナビTECH+のメディアを活用して、自社の魅力を求職者に伝えたいなどお考えの方は、ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
【TECH+マーケティング責任者】武本 大平
2021年からTECH+ のマーケティング部門立ち上げを推進。現在はTECH+マーケティング担当として、 各プロダクトの販促や各種マーケティングアクティビティの立案・実行を担当。マーケティング実務検定3級、SEO検定1級、ネットマーケティング検定を保有。


![[成功事例付き]BtoBブランディングとは?種類・進め方・学習方法まで解説](https://ad-lp.news.mynavi.jp/hubfs/BtoB%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0.webp)