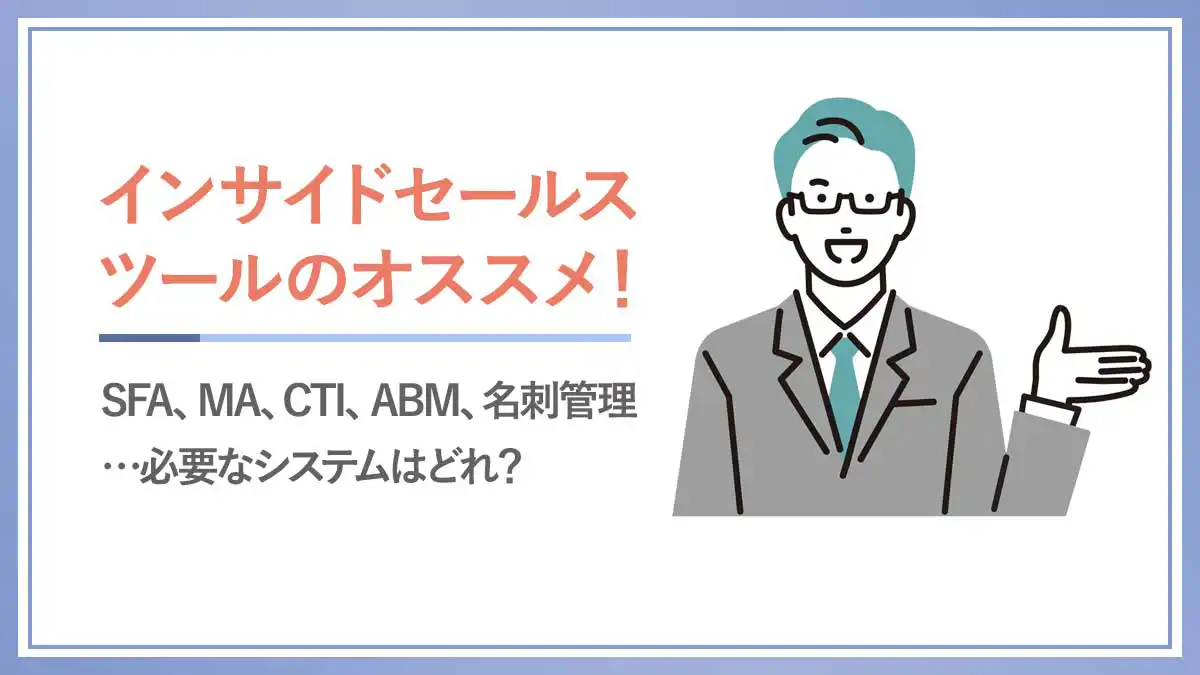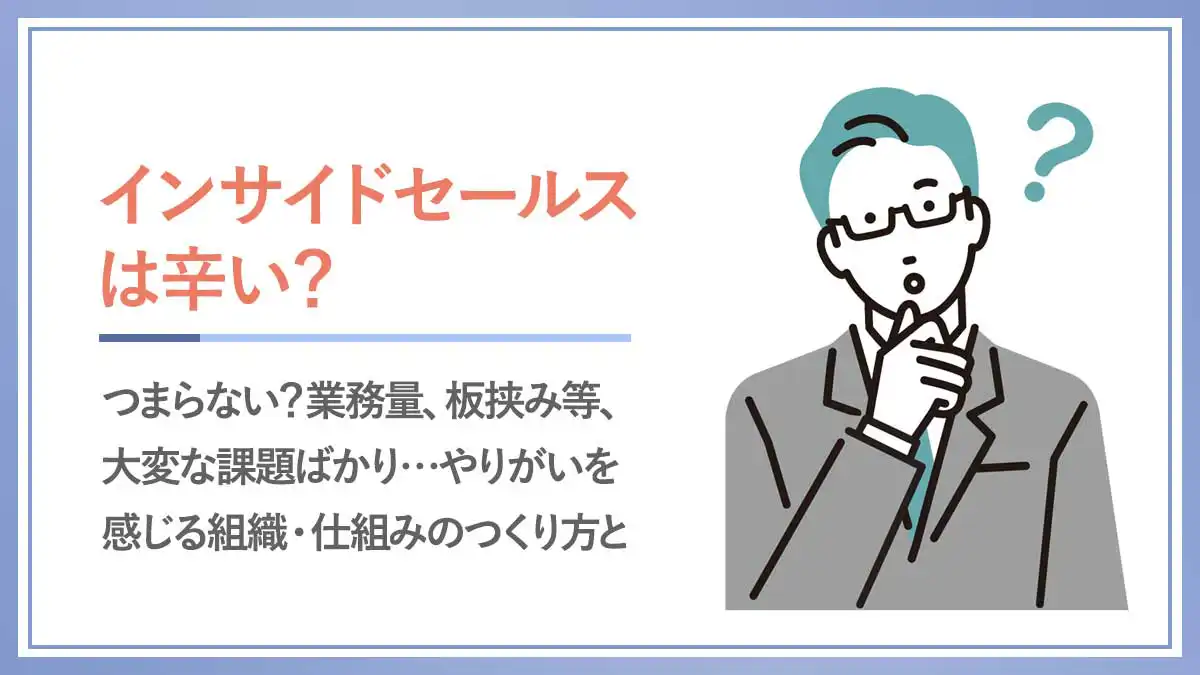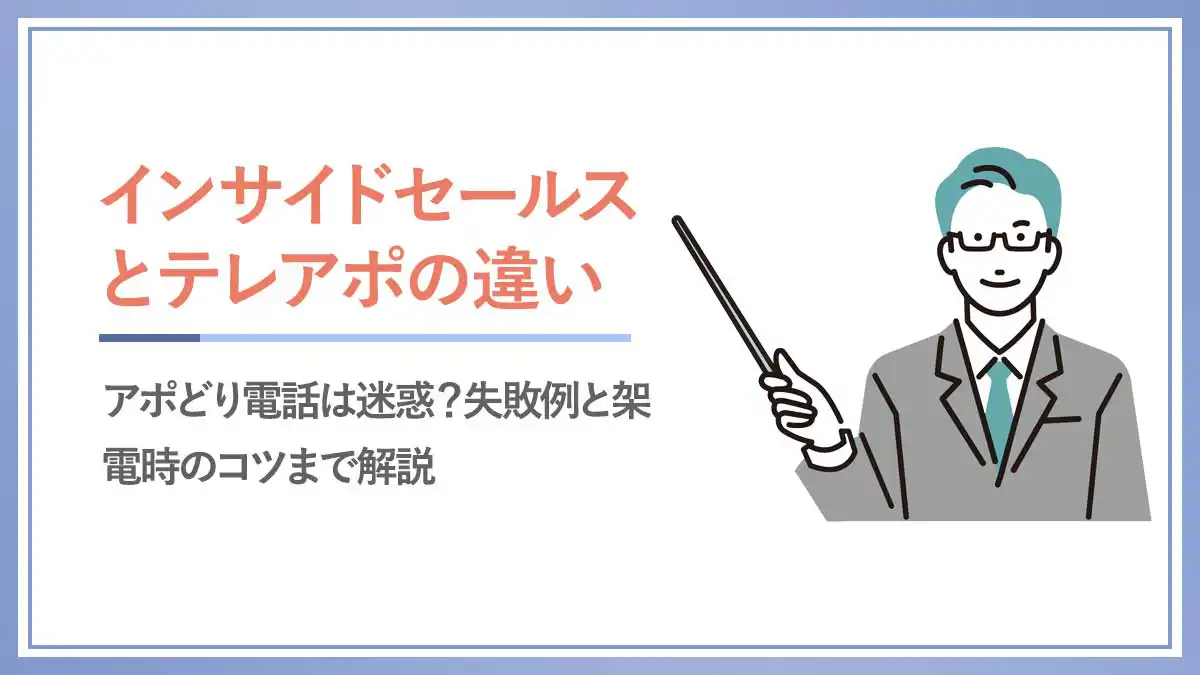【入門編】インサイドセールスとは?基礎知識が身につく9つの解説!
マーケティング
【TECH+マーケティング責任者】武本 大平 [2022.09.21]
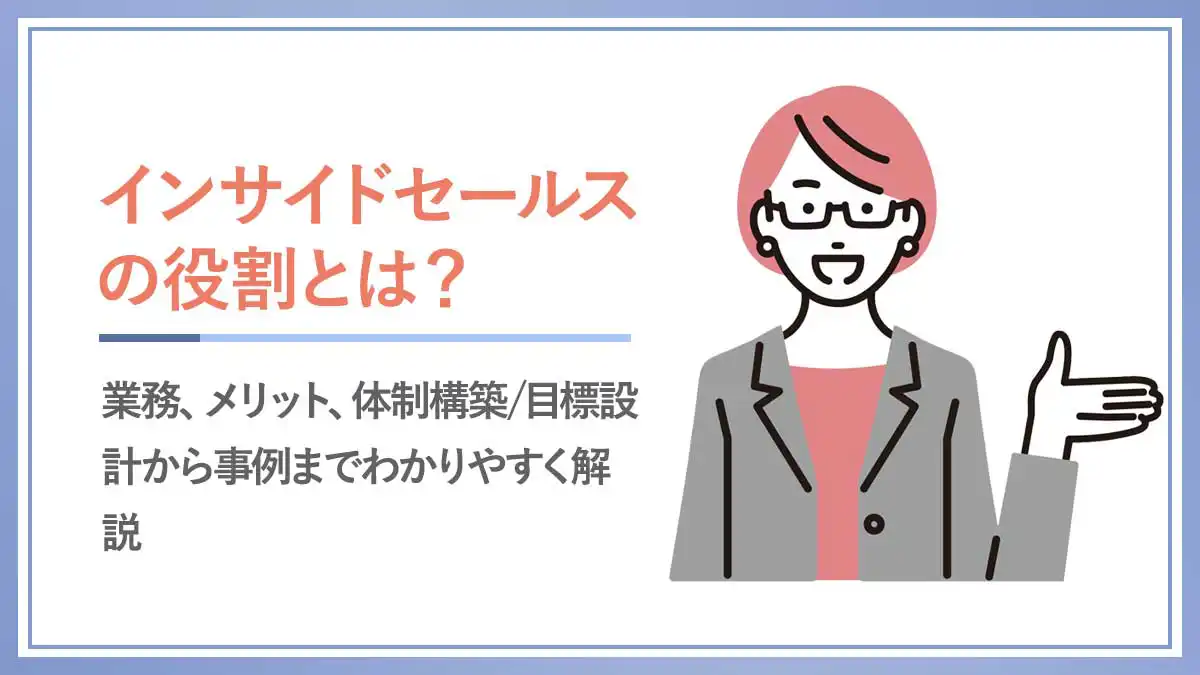
目次
- 【1】インサイドセールスとは?
- 1.フィールドセールスとの違いは?
- 2.テレアポとの違いは?
- 【2】インサイドセールスの業務内容と役割
- 【3】インサイドセールスの種類と目的
- 1.SDR
- 2.BDR
- 【4】インサイドセールスのメリット・デメリット
- メリット(1):営業効率の向上
- メリット(2):コストの削減
- メリット(3):人手不足の解消
- メリット(4):売上予測を立てやすくなる
- デメリット(1):組織作りが難しい
- デメリット(2):信頼関係を構築するのが難しい
- デメリット(3):商品の魅力を伝えるのが難しい
- 【5】インサイドセールスの立ち上げ方・KPI
- STEP1:インサイドセールスの目的を明確にする
- STEP2:シナリオの設計とKPIを設定する
- STEP3:適任者の採用・配置・教育・円滑な組織づくり
- 【6】インサイドセールスの種類別の課題と解決策
- 1.SDRの課題
- SDRの解決策
- 2.BDRの課題
- BDRの解決策
- 【7】インサイドセールスを成功させるコツ
- 1.採用する人材に拘る
- 2.常に他社の取り組みや最新トレンドの情報収集を行う
- 3.インサイドセールスツールの導入
- 4.自社の商材・サービスに合わせたヒアリング項目を決める
- 5.インサイドセールス代行会社に依頼する
- 【8】インサイドセールスの成功事例
- 1.マイナビTECH+
- 2.ビズリーチ
- 3.スリーシーズ
- 【9】インサイドセールスの効率化を図るならTECH+
- 強み①100%セグメントをかけたリードのみを獲得できる
- 強み②高い電話接続率
- 強み③最新の名刺情報
- 【10】まとめ
【1】インサイドセールスとは?
インサイドセールスとは、メールや電話、チャットツールを使用して非対面で行う営業活動をいいます。見込み顧客と信頼関係を深めながら、検討度合を上げるリードナーチャリングが主な役割です。
企業によっては、Web会議ツールで商談・提案まで行い、契約書の取り交わしまで非対面で行うところもあります。
オフィス内から営業活動を行うため、顧客の元に訪問する必要がありません。そのため、移動時間や交通費を削減でき、より多くの顧客に効率的にアプローチできます。
合理的な営業活動方法で、働き方改革が行えるとしてインサイドセールスを導入する企業が増えてきました。
1.フィールドセールスとの違いは?
インサイドセールスとフィールドセールスの違いは「訪問の有無」です。
フィールドセールスとは顧客先を訪問して、対面で営業活動を行うことをいいます。対面で話すことで、顧客との関係をより深めることができます。主な目的は商談して成約を獲得することです。
一方で、インサイドセールスはオフィス内でメールや電話を使用して営業活動を行うことをいいます。主な目的は、見込み顧客の検討度合を上げていくことです。CRMやSFA、MAなどのITツールを使用して顧客の行動(Web閲覧やメール開封)をスコアリングして検討度合を測定しながら、アプローチしていきます。
- インサイドセールスとフィールドセールスの違い
|
特徴 |
フィールドセールス |
インサイドセールス |
|
活動場所 |
顧客先 |
オフィス |
|
コミュニケーション方法 |
対面 |
電話、メール、チャット、ビデオ会議など |
|
目的 |
成約の獲得 |
顧客の育成 営業効率アップ |
下記の記事でインサイドセールスとフィールドセールスの違いについて詳しく解説しています。
・【5分で分かる】インサイドセールスとフィールドセールスの違いとは?連携のポイントも解説!
2.テレアポとの違いは?
インサイドセールスとテレアポは電話を使用する営業手法ですが「目的」が違います。
テレアポの目的はアポイントを獲得することです。営業リストに対して一斉に電話をかけていき、期日までにアポイントを取ります。
一方で、インサイドセールスの目的は、見込み顧客と良好な関係を構築することです。顧客のニーズを把握した上で、相手に必要な情報を提供し、信頼関係を築いていきます。つまり、ナーチャリングが主な目的です。
- インサイドセールスとテレアポの違い
|
特徴 |
テレアポ |
インサイドセールス |
|
取り組み期間 |
短期間 |
長期間 |
|
コミュニケーション方法 |
営業リストに営業 |
顧客に合わせた提案 |
|
目的 |
アポイント獲得 |
関係構築 |
下記の記事でインサイドセールスとテレアポの違いについて詳しく解説しています。
・【比較表付き】5分で分かる!インサイドセールスとテレアポの違い
【2】インサイドセールスの業務内容と役割

インサイドセールスの業務内容はリードナーチャリング(見込み顧客の育成)です。
オフィス内から電話やメール、チャットを使用して顧客と良好な関係を築き、商談の機会を創出する役割を担います。
営業活動を「マーケティング」「インサイドセールス」「営業」の3つのフェーズに分けることで、以下のように各部門が業務に集中できるようになり、営業活動を効率化していけます。
- マーケティング:見込み顧客を創出する
- インサイドセールス:見込み顧客を育成して商談を創出する
- 営業:商談して受注を獲得する
インサイドセールスが見込み顧客を育成することで、営業がより確度の高い商談に集中できるようになるため、成約率が向上します。
このようなメリットがあるため、さまざまな企業が営業活動を分業化し始めました。
【3】インサイドセールスの種類と目的
インサイドセールスの種類には「SDR」と「BDR」があります。それぞれの職種の特徴や目的について理解しておきましょう。
1.SDR
SDR(Sales Development Representative)とは、マーケティング活動で獲得したリードに対して、メールや電話、チャットを使用してアプローチして商談機会を創出します。
例えば、資料請求してくれた顧客にお礼の連絡を入れたり、興味・関心のありそうなセミナーへ招待したりして、自社製品の検討度合を上げていけます。
つまり、マーケティング部門と営業部門の橋渡しが主な役割です。
SDRで営業活動を分業化することで営業効率を上げられるため、リソースが限られている中小企業におすすめの営業活動手法です。
2.BDR
BDR (Business Development Representative)とは、新規顧客開拓を目的として積極的にアプローチしてアポイントを獲得する活動をいいます。
自社のターゲット顧客を一覧にした営業リストを作成していき、意思決定者にアプローチして商談を創出します。CRM/SFAなどのインサイドセールスツールを使用して効率的にアプローチしていくことが大きな特徴です。
新規顧客を開拓し、売上拡大に貢献することが主な役割です。そのため、大企業におすすめの営業活動手法です。
【4】インサイドセールスのメリット・デメリット
インサイドセールスの特徴(メリット・デメリット)は6つあります。
メリット(1):営業効率の向上
インサイドセールスは営業を効率化し、営業組織全体の生産性を高めることができます。
インサイドセールスは、オフィス内で電話やメール、Web会議ツールを用いて見込み顧客にアプローチする営業手法です。顧客先に訪問する必要がないため、移動時間や交通費を削減できます。移動時間がかからないため、より多くの顧客にアプローチすることが可能です。
また、インサイドセールスはCRM/SFAなどのITツールを使いこなします。CRM/SFAツールを用いて成約率の高いアプローチ方法を発見し、組織メンバーに共有すれば、更に営業効率を向上させられます。
メリット(2):コストの削減
インサイドセールスは、オフィス内から電話やメールを用いて顧客にアプローチします。
顧客の元に訪問する必要がないため、交通費や宿泊費などの直接的なコストを削減できます。
また、顧客のもとに移動する時間が削減でき、より多くの時間をアプローチに充てることが可能です。そのため、間接的なコストも削減できます。つまり、顧客獲得コストを抑制できます。
メリット(3):人手不足の解消
インサイドセールスは短時間で多くの顧客にアプローチすることができます。
営業担当者が見込み顧客の育成から商談、提案、契約まで行うと、業務範囲が広くなり、顧客対応の質が低下してしまいかねません。その結果、成約率が低下してしまうのです。このような悩みはインサイドセールスを立ち上げて、営業活動を分業化することで解決できます。
「マーケティング」「インサイドセールス」「営業」が得意とする業務に集中することで、成約率が向上し、結果的に売上も増加させられるのです。そのため、人手不足の悩みを解決するために、働き方改革したい方は営業分業化をおすすめします。
メリット(4):売上予測を立てやすくなる
マーケティング、インサイドセールス、営業は、以下のように連携しています。
|
部門 |
計算式 |
|
マーケティング |
Webサイト来訪者数×獲得率=見込み顧客数 |
|
インサイドセールス |
見込み顧客数×案件化率=案件数 |
|
営業 |
案件数×受注数=受注数 |
インサイドセールス、マーケティング、営業は部門間連携するために、CRM/SFAまたはMAに活動ログを残しています。そのため、見込み顧客の獲得から育成、受注までの一連の過程を数値で把握できるようになり、半年後、1年後、将来的な売上予測がしやすくなります。
デメリット(1):組織作りが難しい
インサイドセールスを立ち上げても、組織作りが非常に難しく失敗してしまうケースが多いです。
なぜなら「マーケティング」「インサイドセールス」「営業」と役割分担を明確にして、部門間連携しなければいけないためです。
役割分担を明確にしなければ、摩擦が生じることもあります。既存の企業文化とチームワークを重視する文化にギャップがある場合は組織全体の変革が必要になることがあります。
また、顧客情報や商談進捗などの情報共有するための仕組み作りが欠かせません。CRMやSFAなどのITツールを導入し、データを蓄積する必要があります。
営業活動を分業化するためには準備が必要となり、組織作りが難しいと挫折してしまう方もいます。
デメリット(2):信頼関係を構築するのが難しい
インサイドセールスは非対面形式でアプローチするため、対面の営業活動と比較すると、相手と信頼関係を構築するのが難しい側面があります。
なぜなら、身振り手振り、表現などの非言語コミュニケーションが制限されてしまうためです。
また、相手の表情を見ることが難しく、共感しづらいという側面もあります。そのため、インサイドセールスで信頼関係を構築するためには、丁寧なコミュニケーションを心がけなければいけません。顧客と上手くコミュニケーションが取れないと挫折してしまう方もいます。
インサイドセールスがきついと思う人もいるため、インサイドセールス部門を立ち上げるときは教育、研修期間を設けるようにしましょう。
デメリット(3):商品の魅力を伝えるのが難しい
インサイドセールスは、商品の魅力を五感で体験してもらえません。商品の魅力を、言葉や写真などで伝えることしかできず、商品の魅力を伝えるのが難しくなります。
対面での営業活動では、顧客に商品を手に取ってもらい、質感や細部のディテールを見せることができます。
しかし、インサイドセールスはそのようなことができず、商品の魅力を十分に理解してもらうことができません。このような問題を解決できるバーチャル試着や360度ビューなどの施策が登場してきているため上手く活用しましょう。
【5】インサイドセールスの立ち上げ方・KPI
インサイドセールスは3STEPで立ち上げます。
STEP1:インサイドセールスの目的を明確にする
まずは営業組織の課題を洗い出して、なぜ、インサイドセールスを導入するのか目的を明確にします。
SDRまたはBDRのどちらを導入すべきかを決めます。その上で、アプローチ対象を決めて「いつ」「どのような」情報を提供するか決めていきましょう。
STEP2:シナリオの設計とKPIを設定する
顧客育成するための道筋を決めて、どのような情報を提供するか決めます。
トークスクリプトを作成しておくと、各メンバーのアプローチ品質を標準化できます。そのため、アプローチ対象を定めたらトークスクリプトを作成しましょう。
また、目標達成の進捗度合を把握できるように、インサイドセールスのKPIを設定します。インサイドセールスのKPIは「メール開封率」「架電数」「荷電率」「商談化数」「商談化率」を設定するケースが多いです。
下記の記事でインサイドセールスのKPIについて詳しく解説しています。
・【見本付き】インサイドセールスで設定すべきKPIとは?自社の改善事例もご紹介!
STEP3:適任者の採用・配置・教育・円滑な組織づくり
インサイドセールスに向いている人の特徴を理解した上で適任者を採用します。
候補者のスキル・マインドを見極めて採用しましょう。 インサイドセールスはきついと感じる人もいて早期離職してしまうこともあるため、ロールプレイングを実施して適任者か見極めることが大切です。
その上で、インサイドセールスが働きやすいようにインサイドセールスツールを導入してあげましょう。インサイドセールスを立ち上げたばかりは失敗することが多いため、相談先を見つけておくと安心できます。
下記の記事でインサイドセールスの立ち上げ方について詳しく解説しています。
・インサイドセールスの立ち上げ(初期構築~設計)で失敗しない始め方と導入のコツ
【6】インサイドセールスの種類別の課題と解決策
インサイドセールスの「SDR」と「BDR」では、それぞれ課題が生じます。インサイドセールスの立ち上げを失敗させないためにも、どのような課題と解決策を把握しておきましょう。
1.SDRの課題
マーケティング活動で獲得したリードに対して、メールや電話を用いてアプローチして商談機会を創出するSDRに取り組むと「顧客からのお問い合わせを商談化できない」という課題が発生しがちです。なぜ、お問い合わせを商談・契約に繋げられないのか原因を見ていきましょう。

株式会社ジード『インサイドセールス取り組み調査2023年最新版』によると、Webサイトからのお問い合わせに対するアプローチ方法で困っている点として「社内にノウハウがない(41%)」「架電しても営業担当社により、アポ獲得率が大きく異なる(29%)」「適切なナーチャリングがわからない(16%)」が挙げられました。
つまり、多くの企業でSDRのノウハウが不足していることが伺えます。
出典元:『株式会社ジード インサイドセールス取り組み調査2023年最新版』
SDRの解決策
SDRに取り組むためのノウハウが不足している場合は、外部パートナーを使用したり講師を招いて研修を実施したりすることが大切です。
マイナビTECH+では、インサイドセールスの代行実績を保有していますが、次のような取り組みをすると顧客からのお問い合わせを商談に繋げられるようになりました。
[商談化の成功事例]
- 問い合わせ内容を丁寧に読み、顧客が本当に求めているものを把握する
- リード獲得チャネル別の接続率を計測して、アプローチの優先順位を決める
- リードにスコアリングを設定してホットリードと判断した場合に電話をかける
2.BDRの課題
新規顧客開拓を目的として積極的にアプローチしてアポイントを獲得するBDRに取り組むと「営業プロセスに工数がかかる」という課題が発生しがちです。

マイナビTECH+が独自調査したところ、工数に時間がかかっているプロセスとして「リスト収集(56.6%)」「リード化(33.1%)」「ナーチャリング(5.63%)」が挙げられました。インサイドセールスに取り組み9割のビジネスパーソンがリスト収集とリード化に課題を感じています。
BDRの解決策
BDRの課題である効率的な営業プロセスを実現するためには、リスト収集からリード化までを外部委託して、自社のインサイドセールスが商談化に注力できる状態に切り替えることで解決できます。なぜなら、リスト収集からリード化までの時間を短縮できるためです。
マイナビTECH+でもテレマ型リード獲得サービスを提供しています。大きな特徴は、マイナビのメディア名義で電話を架けることです。そのため、「しつこく営業電話をかけてくる企業」と企業名に傷を付けずに済みます。
また、電話相手からは営業許可を頂いた上でリードを納品するため、電話の接続率が高いです。そのため、効率的な営業プロセスを実現したいとお考えの方は、リスト収集からリード化までを外部委託することを検討してみてください。
【7】インサイドセールスを成功させるコツ
インサイドセールスを成功させるコツは5つあります。
1.採用する人材に拘る
を成功させるためには採用する人材に拘りましょう。
インサイドセールスは見込み顧客の検討度合を引き上げて商談へ繋げる仕事です。そのため、高いコミュニケーション能力や傾聴力、共感力、粘り強さなどが求められます。
また、「CRM」「SFA」「MA」のデジタルツールを使いこなせるスキルも求められます。
インサイドセールスに向いている人を採用しなければ商談を創出できずに、本人も辛いと早期に退職してしまいがちです。そのため、ロールプレイングなど適性検査を行い、インサイドセールスに向いている人を採用するようにしましょう。
下記の記事でインサイドセールスが辛い理由について詳しく解説しています。
・インサイドセールスは辛い?病む?つまらない?その原因と解決方法を解説!
下記の記事でインサイドセールスに向いている人について詳しく解説しています。
・【適性判断】インサイドセールスに向いている人、不向きな人の特徴
2.常に他社の取り組みや最新トレンドの情報収集を行う
インサイドセールスを成功させるために、他社の取り組みや最新トレンドの情報収集を行いましょう。
日本では2020年にインサイドセールスが普及し、より効率的に商談機会を創出する方法が登場しています。
例えば、近年ではAIなど最新テクノロジーをインサイドセールスに取り入れる動きが出てきました。このような情報収集を行えば、インサイドセールスで商談機会を創出できるようになります。
インサイドセールスの最新トレンドの情報収集は「セミナー」「イベント」「学習サイト」「SNS」「書籍」で行えます。
下記の記事でインサイドセールスにオススメの本について詳しく解説しています。
・【2024年最新版】インサイドセールスにおすすめの本14選!身に付けつけるべきスキル別にご紹介!
3.インサイドセールスツールの導入
インサイドセールスを成功させるためには、リードの一元管理と検討度合のスコアリングが重要です。
つまり、顧客の行動(Web閲覧履歴、メール開封率、セミナー参加)をスコアリングして検討度合いを測定し、受注角度の高い商談を創出しなければいけません。
ITツールを導入してデータ分析することで、それを実現できます。つまり、インサイドセールスは、以下のようなインサイドセールスツールを使いこなせなければいけません。
・主なインサイドセールスツール
|
ツール名 |
主な機能 |
|
CRM(顧客関係管理システム) |
顧客情報の管理、商談履歴の記録、営業活動の進捗管理など |
|
MA(マーケティングオートメーション) |
リード育成、メールマーケティング、キャンペーン管理など |
|
SFA(営業支援システム) |
営業活動の計画、実行、評価など |
|
CTI(コンピューター電話統合) |
電話システムとコンピューターを連携 |
|
ABM(アカウントベースドマーケティング) |
特定の企業をターゲットとしたマーケティング活動 |
|
Web会議ツール |
オンライン会議、画面共有など |
|
名刺管理ツール |
名刺情報のデジタル化、顧客情報の管理 |
|
ドキュメント管理ツール |
提案書、契約書などの管理 |
|
チャットツール |
顧客とのリアルタイムなコミュニケーション |
|
日程調整ツール |
URLでカレンダーを共有して、空いている日時に予約してもらう |
下記の記事でインサイドセールスにオススメのツールについて詳しく解説しています。
・【2024年版】徹底比較!インサイドセールスにオススメのツール26選!
4.自社の商材・サービスに合わせたヒアリング項目を決める
インサイドセールスを成功させるために、自社の商材・サービスに合わせたヒアリング項目を決めておきましょう。なぜなら、商材・サービスによってヒアリング項目は大きく変わるためです。
例えば、クラウド会計ソフト販売会社の場合は「現在、会計処理はどのように行っていますか?」「クラウド会計ソフトで、どのような課題を解決したいですか?」「従業員数は何名ですか?」「月商はいくらですか?」「クラウドサービスの利用経験はありますか?」「業務効率化を検討していますか?」とヒアリングします。
これらの情報を入手できれば、自社サービスを売り込みやすくなります。
下記の記事でインサイドセールスのヒアリング項目について詳しく解説しています。
・インサイドセールスのヒアリング項目設計は?アポ獲得率の上げ方は?受付突破方法は?段階別に課題と対策を紹介
5.インサイドセールス代行会社に依頼する
インサイドセールスを代行会社に依頼することも選択肢の一つです。
インサイドセールスを代行会社に依頼すれば、インサイドセールスの専門知識を持つプロに営業活動をお任せできます。インサイドセールスの早期立ち上げも可能です。
自社でインサイドセールスを採用する必要がないため、人件費や教育費などの固定費を抑えられます。そのため、リソース不足やノウハウ不足で悩んでいる方は、インサイドセールス代行会社への依頼を検討してみてください。
下記の記事でインサイドセールス代行会社について詳しく解説しています。
・インサイドセールス代行会社18社比較!選定する時のポイントもご紹介!
【8】インサイドセールスの成功事例
インサイドセールスで商談を創出できている企業は、どのような取り組みをしているのでしょうか?インサイドセールスの成功事例を確認しておきましょう。
1.マイナビTECH+
マイナビTECH+はインサイドセールス部門を設置した当初、インサイドセールスが足りずに商談化件数の目標に届かない状況でした。しかし、次のような取り組みで、少数精鋭で目標を達成することができました。
- 自動返信メールと日程調整ツールの活用
マイナビTECH+の各資料がダウンロードされた際に、個別に自動返信メールを設定して、メール内に日程調整ツールのURLを埋め込み、顧客の都合が良い日時に商談が設定できるように工夫しました。この施策により、アプローチ効率が上がり、商談化率の改善に繋げることができました。
- チャネル別の接続率・トスアップ率を分析
リード獲得チャネル別の接続率やトスアップ率を定量的に分析して、アプローチの優先順位を決めました。その結果、効率的なアプローチが可能となりました。
2.ビズリーチ
ビズリーチは、転職支援サービスを提供している会社です。ビズリーチは、従来はアウトバウンド営業を中心に行っていました。テレアポで営業をかけていましたが、商談化の確率の低さに悩んでいたようです。
また、商談化しても契約までのリードタイムが1ヶ月以上と長いことも課題となっていました。このような悩みを解決するために、ビズリーチはアウトバウンド営業からインバウンド営業に切り替えることにしたのです。
ビズリーチのテレビCMでお問い合わせをしてくれた見込み顧客に対して、インサイドセールスがオンライン対応することで、商談件数を飛躍的に向上させることができました。また、リードタイムも17日まで短縮することに成功しました。
3.スリーシーズ
スリーシーズは法人向けの営業支援サービスを提供している会社です。同社は、訪問営業を行っても断られてしまうことに課題を感じていました。
電話で訪問アポイントを取った上で訪問しても話を積極的に聞いてもらえていなかったのです。そこで、インサイドセールスを導入して、オンラインデモを体験してもらう営業手法に切り替えました。
オンラインで気軽に参加できるとして、顧客からのアポイントが取りやすくなり、案件受注率も3倍に伸ばすことができました。
【9】インサイドセールスの効率化を図るならTECH+
インサイドセールスを効率化したい方は、マイナビTECH+のテレマ型リード獲得サービスがおすすめです。ここでは、テレマ型リード獲得サービスの強みを簡単にご紹介します。
強み①100%セグメントをかけたリードのみを獲得できる
マイナビTECH+は全国840万社の顧客リストを保有しているため、お客様のご要望を聞いた上で、ターゲットをリスト化できます。
お客様がターゲットとする方のみにアプローチするため、見込み度が低く、商談化に繋がりにくいという課題を解決できます。
自社に営業リストがないとお悩みを抱えている方は、マイナビTECH+テレマ型リード獲得サービスの利用を検討してみてください。
強み②高い電話接続率
マイナビTECH+のテレマ型リード獲得サービスはマイナビニュース名義でお客様に電話をかけます。お客様と策定したコール内容で電話をかけます。
また、情報提供及び営業許諾を取得したお客様をリードとして納品しているため、フォローコールの接続率が高いです。そのため、質の高いリードが欲しいという方のご要望に応えられます。
強み③最新の名刺情報
マイナビTECH+のテレマ型リード獲得サービスは、電話の際に相手から名刺情報をヒアリングします。そのため、お客様に納品するリードは全て最新情報です。
アフターコールをした際に「担当者が退職した」「担当者が部署を移動した」などで、電話が繋がらないという事態にもなりません。そのため、最新情報に刷新された営業リストが欲しい方にもおすすめです。
【10】まとめ
インサイドセールスとは、メールや電話、Web会議ツールを活用しながら非対面形式で行う営業活動をいいます。インサイドセールスの業務内容はリードナーチャリング(見込み顧客の育成)です。
インサイドセールスを立ち上げることで、「マーケティング」「インサイドセールス」「営業」がコア業務に集中できるようになり、営業活動を効率化できます。この記事では、インサイドセールスの立ち上げ方や成功のポイントをご紹介したため、ぜひ取り組んでみてください。
また、マイナビTECH+では営業リスト収集からリード化までを代行するテレマ型リード獲得サービスを提供しています。100%セグメントをかけたリードを獲得したい方は、ぜひお気軽にご相談ください。
【TECH+マーケティング責任者】武本 大平
2021年からTECH+ のマーケティング部門立ち上げを推進。現在はTECH+マーケティング担当として、 各プロダクトの販促や各種マーケティングアクティビティの立案・実行を担当。マーケティング実務検定3級、SEO検定1級、ネットマーケティング検定を保有。