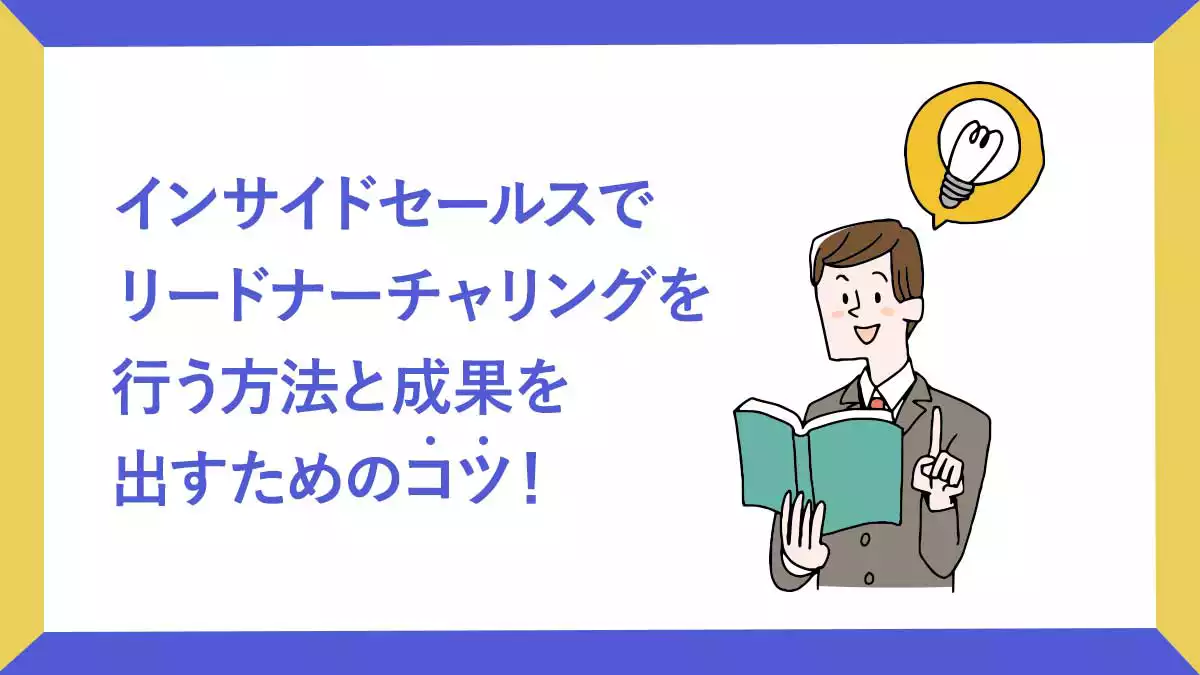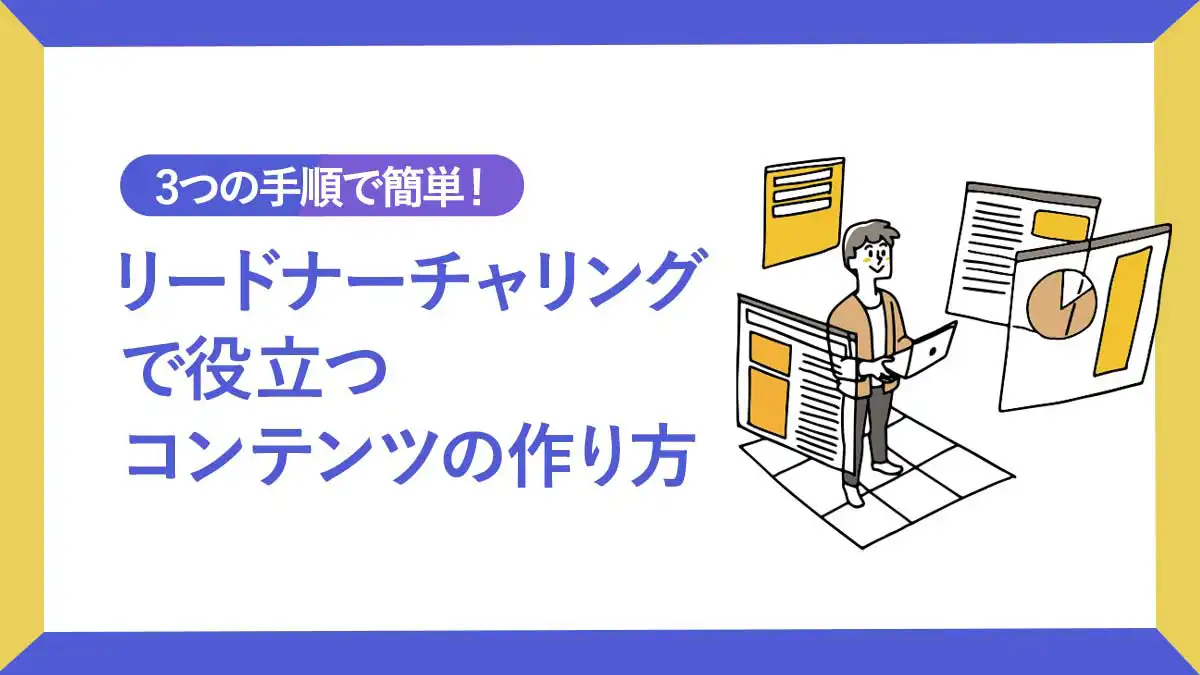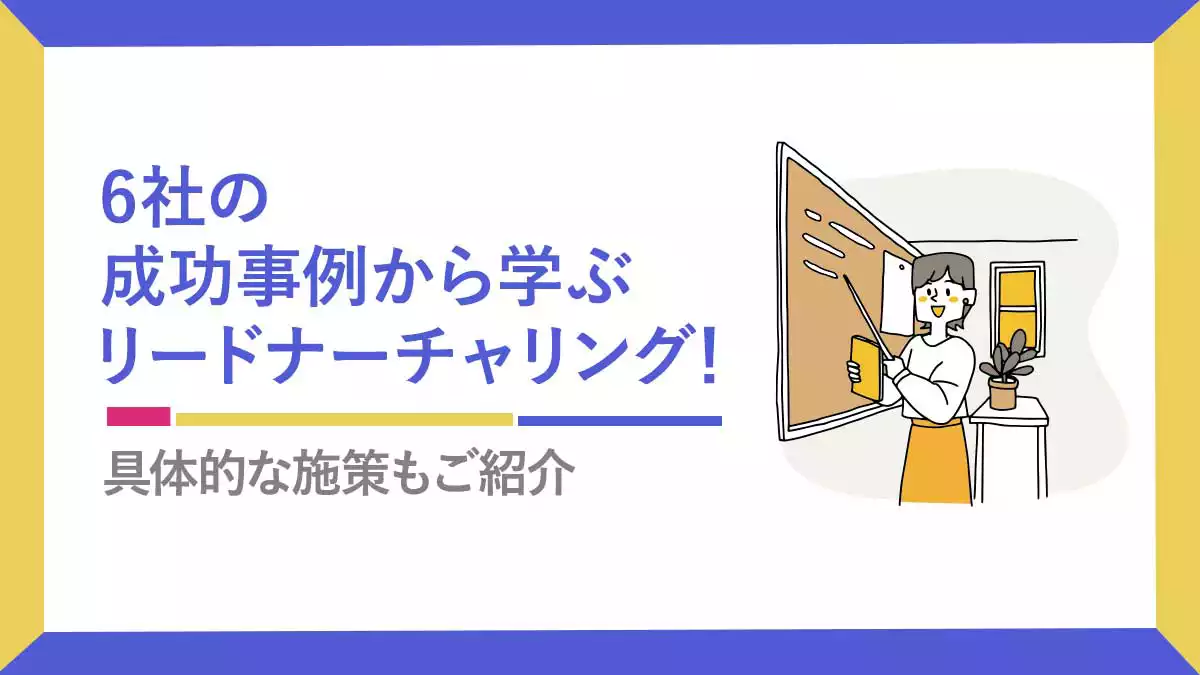【入門編】リードナーチャリングとは?失敗しない基本のプロセスや事例を解説!
ナーチャリング
【TECH+マーケティング責任者】武本 大平 [2022.06.27]
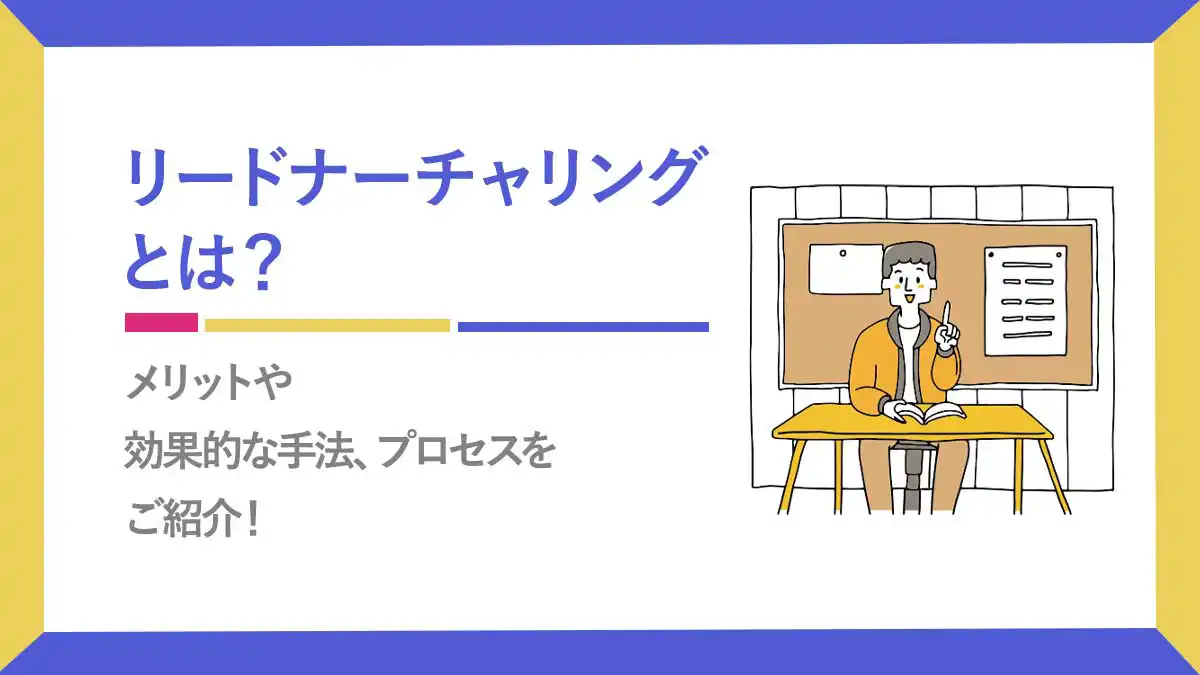
目次
- 【1】リードナーチャリングとは?
- 【2】BtoBマーケティングでのリードナーチャリングの役割
- 【3】リードナーチャリングの重要性・メリット
- 1.顧客の取りこぼしを減らして費用対効果を高めるため
- 2.購買プロセスの変化に対応するため
- 3.機会損失を防ぐため
- 4.受注角度が高いリードに営業リソースを投下するため
- 【4】リードナーチャリングを始めるプロセス
- 1.リード情報を一元管理する
- 2.ユーザーのフェーズを設計する
- 3.フェーズごとの手法・コンテンツを考える
- 4.フェーズ毎の施策を実施
- 5.効果測定を行う
- 【5】リードナーチャリングの効果を高めるポイント
- 1.KPIを設定する
- 2.ホットリードの定義を明確にする
- 3.リード獲得の手法を見直す
- 4.MAツールを導入する
- 5.CRM/SFAで部門同士で情報を共有する
- 【6】リードナーチャリングに効果的な6つの手法・施策
- 1.メール
- 2.インサイドセールス
- 3.セミナー
- 4.オウンドメディア
- 5.SNS
- 6.リターゲティング広告
- 【7】リードナーチャリングの活用事例
- 1.株式会社マイナビ(TECH+)
- 2.日本電気株式会社
- 3.Oktopost社
- 【8】TECH+ならリード獲得からナーチャリングまで一気通貫でご支援
- 1.特定ターゲットに絞り込める
- 2.リード獲得件数が保証されている
- 3.一気通貫型サービスを提供
- 【9】まとめ
【1】リードナーチャリングとは?
リードナーチャリングとは、企業と接点を持ったことがある見込み顧客の購買意欲を高めて商談や受注に繋げるマーケティング活動をいいます。見込み顧客の中には、商談したけれど受注に至らなかった失注顧客や休眠顧客も含まれます。
見込み顧客に対して有益な情報を提供して良好な関係を築いておき、商品・サービスの検討度を上げて、商談、受注へと繋げる活動です。
商品・サービスを購入するまでの検討期間が長いBtoBビジネスや、不動産や金融商品などの高額商材を売るBtoCビジネスに有効な施策と言われています。
【2】BtoBマーケティングでのリードナーチャリングの役割

BtoBマーケティングにおけるリードナーチャリングの役割は、見込み顧客の育成です。
リードナーチャリングは、デマンドジェネレーション(見込み顧客を創出して営業部門へ渡すマーケティング活動)の1つです。リードナーチャリングの役割を理解するためにも、デマンドジェネレーションの流れを覚えておきましょう。
|
[デマンドジェネレーションの流れ] |
下記の記事でリード獲得について詳しく解説しています。
・リード獲得とは?効果的な最新手法20選から事例までご紹介!
下記の記事でホワイトペーパーについて詳しく解説しています。
・ホワイトペーパーとは?意味や種類から具体的な成功事例まで解説!
下記の記事でリードクオリフィケーションについて詳しく解説しています。
・リードクオリフィケーションとは?成果に繋がる5つの手法を解説!
【3】リードナーチャリングの重要性・メリット
リードナーチャリングを行うメリットは3つあります。
1.顧客の取りこぼしを減らして費用対効果を高めるため
営業活動では、受注に繋がる見込み度が高い顧客を優先してアプローチしていきます。商品・サービスの導入時期が半年後や1年後の見込み顧客のアプローチは後回しにされてしまいがちです。その結果、顧客の取りこぼしが発生してしまいます。
例えば、顧客単価が1万円で50件の取りこぼしがあった場合、50万円を無駄にしてしまうことになります。このような取りこぼしは、リードナーチャリングで顧客と接点を持っておくことで解消できます。
2.購買プロセスの変化に対応するため
インターネットが普及して、1人1台スマートフォンを保有する時代となり、顧客の購買プロセスはAIDMAからAISASへ変化してきました。
|
AIDMA |
AISAS |
|
Attention(注意) Interest(関心) Desire(欲求) Memory(記憶) Action(行動) |
Attention(認知・注意) Interest(興味・関心) Search(検索) Action(行動) Share(共有) |
従来は商品に興味・関心が湧き、欲しいと思ったら、企業にお問い合わせしていました。しかし、インターネットの普及により、商品に興味・関心が湧いて欲しいと思ったら「本当に良い商品なのだろうか?」「他社製品にはどのようなものがあるのだろうか?」と検索して、比較検討するようになりました。
このような変化に伴い、顧客が比較・検討する中で離脱してしまわないように、良好な関係を築く必要性が出てきたのです。そのため、リードナーチャリングが重要だと言われています。
3.機会損失を防ぐため

リードナーチャリングはビジネスの機会損失を防ぎます。なぜなら、リードナーチャリングを行わずに接点がなくなれば、顧客が他社商品を購入してしまうためです。
お問い合わせしたにも関わらずフォローしてもらえない場合「別の会社の方が親身に相談に乗ってもらえそうだ」と感じます。このような気持ちになり、競合他社で契約してしまうのです。
欧米のマーケティングコンサルティングファームのSirius Decision社の調査結果では、リードナーチャリングを行わなければ、見込み顧客の80%が2年以内に競合他社から製品を購入するという事実が判明しています。そのため、ビジネス機会を損失しないためにも、リードナーチャリングに取り組むようにしましょう。
4.受注角度が高いリードに営業リソースを投下するため
リードナーチャリングを行えば、営業部門は受注確度が高い見込み顧客対応にリソースを投下できます。商談の準備を入念に行えて、契約率を上げられます。営業活動を効率化するためにも、リードナーチャリングを行いましょう。
営業部門に受注確度が高い顧客を引き渡すためには、MQLを定義しておくと、部門間連携が上手く行くようになります。
下記の記事でMQLについて詳しく解説しています。
・【これだけ読めばOK】MQLとは?SQLとの違いや事例をご紹介!
【4】リードナーチャリングを始めるプロセス

リードナーチャリングの手順は以下の通りです。
- リード情報を一元管理する
- ユーザーのフェーズを設計する
- フェーズごとの手法・コンテンツを考える
- フェーズ毎の施策を実施
- 効果測定を行う
ここでは、それぞれの手順について解説します。
1.リード情報を一元管理する

まずは、リード情報をハウスリストにして一元管理しましょう。Webサイトからのお問い合わせや展示会での名刺交換など、さまざまな方法でリードを獲得すると情報が整理されておらず扱いづらいです。
そのため、ハウスリストに記載する項目を決めて名寄せを行い整理していきましょう。リード情報を上手く管理するコツは、項目を増やし過ぎないことです。またデータの紛失などがないようにCRM/SFAなどのITツールで管理することも大切です。
下記の記事でハウスリストについて詳しく解説しています。
・ハウスリストとは?インサイドセールスやメルマガなど活用方法を解説
下記の記事でリード獲得について詳しく解説しています。
・名寄せとは?実施手順やおすすめのツール7選をわかりやすく解説
2.ユーザーのフェーズを設計する

リードナーチャリングを行う際は、見込み顧客の購入フェーズを踏まえながらアプローチすることが大切です。購入フェーズは「情報収集」「興味関心」「比較検討」「商談」に大きく分けられ、どのフェーズかアプローチ方法が変わります。そのため、まずは購買フェーズ毎のアプローチ方法を設計しましょう。
3.フェーズごとの手法・コンテンツを考える

購買フェーズの条件を決めたら、手法とコンテンツを決めていきます。これらを、明確に決めておけば、リードナーチャリングがスムーズに行えるようになります。
下記の記事でリードナーチャリング向けのコンテンツについて詳しく解説しています。
・【4つの手順で作れる】リードナーチャリング用のコンテンツの作り方
4.フェーズ毎の施策を実施
次に見込み顧客の検討度をフェーズ別に分類して、コンテンツを提供していきます。
例えば、情報収集段階の見込み顧客に対しては、商材に興味を持ってもらうために、よくある悩みを解決する方法をノウハウで提供してあげましょう。
その一方で、比較・検討の段階の見込み顧客には、導入事例を提供して、どのような効果が見込めたのかを教えてあげると、稟議に通してもらえるようになります。
5.効果測定を行う
最後にリードナーチャリングの効果測定を行いましょう。効果測定には「コンテンツの反応」「営業パス数」の2通りの方法があります。
- コンテンツの反応
フェーズ毎でコンテンツを提供したら「閲覧されているか」「内部リンクをクリックされているか」を確認しましょう。提供したコンテンツが顧客ニーズとずれている場合は、反応が鈍くなります。そのため、コンテンツの反応を見ながら内容を改善していきましょう。
- 営業へのパス数
営業へ見込み顧客をパスできていなければ、リードナーチャリングは成功しているとは言えません。見込み顧客とコミュニケーションを取ることだけに専念せず、商談化できているか確認するようにしましょう。
商談化件数などKPIを設定して、達成できているか確認してください。もし、KPIが達成できていない場合は、フェーズ別のアプローチ方法やコンテンツ内容がニーズと相違していないかを確認しましょう。
【5】リードナーチャリングの効果を高めるポイント
リードナーチャリングの手順をご紹介しましたが、ポイントを押さえておくと、より高い効果が見込めるようになります。リードナーチャリングの効果を高めるポイントは5つあります。
1.KPIを設定する
リードナーチャリングを行う前に、KPIを設定しましょう。
KPI(重要業績評価指標)を定めておくことで、理想と現実の差分を正しく把握できるようになり、リードナーチャリングの施策をPDCAで回して改善できます。
KPIを設定する際は「Specific:具体的」「Measurable:測定可能」「Achievable:達成可能」「Relevant:上位目標と関連する」「Time-bound:明確な期限」を設定すると、施策の効果検証がしやすくなります。
下記の記事でリードナーチャリングのKPIについて詳しく解説しています。
・リードナーチャリングのKPI設定方法!設計例付きで今日から使える!
2.ホットリードの定義を明確にする
リードナーチャリングに取り組む前に、ホットリードの定義を明確にしておきましょう。ホットリードとは、見込み度が高い顧客をいいます。どのような状態を見込み度が高いと言うのかを明確にしておき、マーケティング部門と営業部門の認識を合わせておきましょう。
認識を合わせておかなければ、営業部門から「マーケティング部門から渡されるリードの質が悪い」と言われてしまい、営業活動の効率が悪くなります。このようなトラブルを防止するためにも、ホットリードの定義を明確にしておきましょう。
下記の記事でホットリードについて詳しく解説しています。
・ホットリードとは?今から実践できる5つの獲得方法をご紹介!
3.リード獲得の手法を見直す
リードナーチャリングで効果を上げるためには、リード獲得の手法を見直すことも大切です。
例えば、マイナビTECH+の独自調査ではテレマーケティングでリードナーチャリングしやすい施策と、リードナーチャリングしにくい施策があることが判明しています。
[リードナーチャンリグしやすい施策]
- 第1位:ホワイトペーパーからのリスト 49%
- 第2位:製品比較系サービスへの出稿からのリスト 41%
- 第3位:展示会出展からのリスト36%
[リードナーチャンリグしにくい施策]
- 第1位: 外部メディアの集合型イベント出展からのリスト 39%
- 第2位:展示会出展からのリスト 37%
- 第3位:製品比較系サービスへの出稿からのリスト 34%
参考:『【調査レポート】コロナ過におけるテレマーケティングの実態!204名のテレマ担当の声から今を読み解く!』
そのため、リードナーチャリングがしにくいと感じたら、リード獲得手法を見直してみることをおすすめします。
下記の記事でリード獲得について詳しく解説しています。
・リード獲得とは?効果的な最新手法20選から事例までご紹介!
4.MAツールを導入する
リード数が増えると、1人1人とコミュニケーションするのが難しくなってきます。このような悩みを抱えたら、MAツール(マーケティングオートメーションツール)を導入しましょう。
MAツールはリードをセグメント分けして、メールを配信できます。また、メールの開封率やリンクのクリック数、展示会来訪の行動履歴を管理してスコアリングすることも可能です。
効率的にリードナーチャリングするために欠かせないツールのため、少人数で多くのリードを育成したい場合はMAツールを導入しましょう。
5.CRM/SFAで部門同士で情報を共有する
リードナーチャリングの効果を最大化するために、見込み顧客に関する情報を共有するようにしましょう。基本的にマーケティング部門がリードナーチャリングを行い、営業部門に購買意欲が高まった顧客を引き継ぎます。
顧客を引き継ぐ際に「どのような媒体を経由してお問い合わせしてきたのか?」「自社商品に興味・関心を持った理由とは?」などを共有しておくと、営業部門は顧客によりよい提案ができるようになり、受注に至りやすくなるのです。
そのため、見込み顧客に関する情報はCRM/SFAに入力して、社内で共有するようにしましょう。
下記の記事でリード獲得に必要なツールについて詳しく解説しています。
・リード獲得に必要なツールとは?自社に導入すべきツールと利用するメリット・デメリット
リード獲得に必要なツールを知りたい方はこちら!
下記の記事では、リード獲得に必要なツールについて詳しく解説しています。
リード獲得に必要なツールとは?自社に導入すべきツールと利用するメリット・デメリット
【6】リードナーチャリングに効果的な6つの手法・施策
リードナーチャリングで効果を出すためには手法・施策選びも重要です。リードナーチャリングに効果的な手法・施策は6つあります。
1.メール

メールを活用すると、こちら側の都合で顧客育成を行えます。なぜなら、送信相手、日付、曜日を設定した上でメールを配信できるためです。また、他の施策と比較して準備するものもなく、お金もかからないため手軽に行えます。メールの開封率やクリック数を測定して内容を改善することも可能です。
また、メルマガ形式やセグメント配信、ステップメールなど最適な方法を選ぶことで、効果が見込めるようになります。メールは導入ハードルも低いため、どのような方にもおすすめの施策です。
下記の記事でメールを活用したリードナーチャリング方法について詳しく解説しています。
・リードナーチャリングをメールで行う6つの方法!
2.インサイドセールス

インサイドセールスを活用すると、顧客の反応を見ながら関係を構築できます。
インサイドセールスとは、自社と接点を持つ見込み顧客に対して、非対面(電話やメール、Wen会議)でコンタクトを取り、商談化を目指す手法をいいます。
コロナ禍でリモートワークが定着し、インサイドセールスが広まりました。
インサイドセールスのメリットは、見込み顧客にアプローチをして反応を見ることで見込み度を測定できることです。見込み度が高い顧客は、そのまま商談化できるため、リードタイムを短縮できます。そのため、営業活動を効率化したい方におすすめの施策です。
下記の記事でインサイドセールスについて詳しく解説しています。
・インサイドセールスとは?役割・業務、メリット、体制構築/目標設計から事例までわかりやすく解説
3.セミナー

セミナーを開催すると、見込み顧客と会う機会が得られて、深い関係を築けます。なぜなら、セミナーテーマに関して強い興味・関心を持っている人が自主的に参加しているためです。そのため、こちらの話を真剣に聞いてくれます。
しかし、セミナーの内容が薄く、役に立たない内容なら不満を持たれてしまいます。その結果、セミナー参加者との関係が悪化してしまうでしょう。そのため、セミナーを開催する場合は参加者が「セミナーに参加して良かった」と思ってもらえるものを準備してください。
下記の記事でセミナーについて詳しく解説しています。
・セミナーとは?参加満足度が高いイベントを開催するための手順を紹介
下記の記事でウェビナーについて詳しく解説しています。
・ウェビナーとは?年間100件以上開催したプロが基礎を徹底解説!
4.オウンドメディア

オウンドメディアで有益な情報を発信すれば、見込み顧客に好感を抱いてもらえます。「興味のあることについて詳しく知っている企業だ」と信頼をしてもらえて、購買意欲が高まったときに真っ先に相談してもらえるでしょう。
オウンドメディアを活用してリードナーチャリングを行うメリットは、プル型のため相手に受け入れてもらえることです。また、オウンドメディアを運営すれば、同時に不特定多数の人との関係を育成できます。
下記の記事でBtoBオウンドメディアについて詳しく解説しています。
・BtoBオウンドメディアとは?メリット・デメリット、手順まで解説
5.SNS

SNSを運営すれば、見込み顧客に定期的にコンタクトを取れます。企業側の一方的な情報発信になりがちですが、いいねやコメントなどがもらえることもSNSの魅力です。好意を抱いてもらえれば、SNS投稿内容に反応がもらえるだけでなく拡散してもらえます。つまり、会社のプロモーションにも役立ちます。
SNSは費用がかからないためハードルは低いですが、炎上リスクがあることを理解しておき、炎上対策をした上で運営しましょう。
6.リターゲティング広告

リターゲティング広告を配信すれば、見込み顧客が自社の存在を忘れてしまわないように防止できます。
リターゲティング広告とは、自社のサイトへ訪問したことがある見込み顧客に対して配信できる広告です。GoogleやYahoo!と提携している媒体の広告枠に広告を配信でき、追随する形となります。そのため、商品の比較・検討の段階で自社の存在を忘れて欲しくないとお考えのときにおすすめの手法です。
【7】リードナーチャリングの活用事例
リードナーチャリングを実施している企業は、どのような効果が見込めているのでしょうか?ここでは、リードナーチャリングの成功事例をご紹介します。
1.株式会社マイナビ(TECH+)

マイナビTECH+では、「マーケティング部門」「インサイドセールス部門」「フィールドセールス部門」で分業化し、ホットリードやリードサイクルを見直すことでリードナーチャリングに成功しました。
以前までは資料〇件をダウンロードした人をホットリードに設定していましたが、営業部門から見込み度が低いと言われていました。そこで、営業部門に「どのような経路のリードが商談に繋がっているのか」「なぜ、顧客は自社サービスに興味を持ったのか」などをヒアリングして、ホットリードの定義を見直しました。
BtoB商材はターゲットが少ないため、いつか新規顧客の獲得件数が頭打ちになってしまいます。そのため、現在保有しているリードを中心にリードナーチャリングを行いました。このようなマーケティング施策の変更で、商談数を前期比1.5倍に伸ばすことができました。
2.日本電気株式会社
 出典元:『日本電気株式会社 公式ホームページ』
出典元:『日本電気株式会社 公式ホームページ』
日本電気株式会社は、2016年9月にインサイドセールス部門を立ち上げ・拡大しました。
これまで、見込み顧客の育成は担当者ベースで行ったり、外部委託に依頼したりなどしていました。バラバラに散らかっていたリードナーチャリング業務を集約し、インサイドセールス部門が行うように変更しました。
マーケティング部門とインサイドセールス部門が連携して、リードジェネレーションからリードナーチャリング、リードクオリフィケーションまで担当しています。そして、見込み度が高い顧客をフィールドセールスに引き渡すなどして、効率的な営業活動を実現しています。
3.Oktopost社
 出典元:『Oktopost公式ホームページ』
出典元:『Oktopost公式ホームページ』
ソーシャルメディア管理サービスを提供しているOktopost Technologies社は「メール」「電話」「SNS」で、見込み顧客のリードナーチャリングを実施しています。
自社商品のトライアル版を「使用していない人」「使用中の人」「使用後の人」に分類して、MAツールを用いてメールを配信しています。メールからサイトにクリックしてホワイトペーパーをダウンロードした人に対しては電話でフォローアップして自社商品の受注率を高めています。
また、Skypeなどのチャットツールで、トライアル中の不明点を気軽に聞けるような仕組みを整えて、顧客との信頼を構築しています。
下記の記事でリードナーチャリングの成功事例について詳しく解説しています。
・7社の成功事例から学ぶリードナーチャリング!ポイントもご紹介
【8】TECH+ならリード獲得からナーチャリングまで一気通貫でご支援
もしBtoBマーケティングでリード獲得やリードナーチャリングでお悩みを抱えたら、マイナビTECH+へご相談ください。マイナビTECH+がお客様のお悩みを解決致します。ここでは、マイナビTECH+が提供するBtoBマーケティング支援サービスの特長をご紹介します。
1.特定ターゲットに絞り込める
マイナビTECH+のBtoBマーケティング支援サービスは特定ターゲットに絞り込んでアプローチすることができます。マイナビTECH+はITに特化した媒体を運営しているため、ITや製造会社の方の特定ターゲットに絞り込んだリードをお渡しできます。
2.リード獲得件数が保証されている
BtoBマーケティング支援サービスはリード獲得件数が保証されていないケースが多く見受けられますが、マイナビTECH+は保証したリード獲得件数をお渡しします。1件のリード獲得コスト〇万円と計算できるため、マーケティングの計画が立てやすくなります。
3.一気通貫型サービスを提供
マイナビTECH+のBtoBマーケティング支援サービスは、リード獲得からナーチャリングまで一気通貫の支援も可能です。リード獲得だけでなく、商談化まで行って欲しいというご要望にも応えることができます。そのため、マーケティング業務を代行したいとお考えの方は、お気軽にご相談ください。
下記の記事でTECH+の導入事例について詳しく解説しています。
・マイナビTECH+のBtoBマーケティング導入事例はこちら
【9】まとめ
リードナーチャリングとは、企業と接点を持ったことがある見込み顧客の購買意欲を高めて、商談や受注に繋げるためのマーケティング活動をいいます。
お問い合わせしたにも関わらずフォローしてもらえない場合、「別の会社の方が親身に相談に乗ってもらえそうだ」と感じてしまうでしょう。このような気持ちになり、競合他社で契約してしまいます。このようなビジネス機会の損失を防ぐためにも、リードナーチャリングを行うようにしましょう。
この記事では、リードナーチャリングの方法をご紹介しましたが、支援会社を利用するのも1つの選択肢です。マイナビTECH+では、BtoBマーケティング支援サービスを提供しています。リード獲得からリードナーチャリングまで通気一貫でサポートできるため、マーケティングに関するお悩みを抱えている方は、お気軽にご相談ください。
【TECH+マーケティング責任者】武本 大平
2021年からTECH+ のマーケティング部門立ち上げを推進。現在はTECH+マーケティング担当として、 各プロダクトの販促や各種マーケティングアクティビティの立案・実行を担当。マーケティング実務検定3級、SEO検定1級、ネットマーケティング検定を保有。